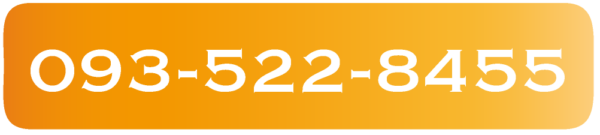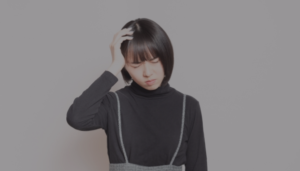子供の疳(かん)の虫でお困りではありませんか?
キーキー泣きわめく(ギャン泣き)、すぐ怒る、ものを投げる、頭を壁などにぶつけたがる、髪を自分で抜いていまう、など一度起こると手がつけられず、困ってしまう状態を疳の虫といいます。
これから疳の虫の原因と対処法もお伝えしますので、ぜひ最後までお付き合いください。
時間のない方は対処法だけでもお読みください。
原因がわかった方が、より対策は取りやすかったり、前触れがわかるので、時間がある時に読み返してみてくださいね。
大人のイライラ(怒り)をコントロールする方法(アンガーマネジメント)

陽気が盛んだから疳の虫が起こる
子供は基本的に陽気が旺盛です。
陽気とは簡単に説明すると、温める気(エネルギー)です。
陽気は上に昇る性質があるので、その陽気がありあまって疳の虫を引き起こしてしまいます。
なので、イライラして頭を壁にぶち当てたり、髪を引っこ抜いたり、泣き喚いて、陽気を発散させているんですね(癇癪(かんしゃく)といったりもしますね)。
疳の虫を起こす子供の特徴
疳の虫を起こしやすい子供は、体が硬い傾向があります。なので、、、
- 肌がごわついている
- 頭皮が硬い
- 髪の毛が逆立っている
- 鼻やおでこに青筋がある
- 目がつりあがってる
- お腹が硬い
- 便秘がち
お子さんが、これらの状態に当てはまるようなら、疳の虫が起こりやすいと言えます。
小児鍼の効果
小児鍼の一般的な効果はこちらをご覧ください。
小児鍼で疳の虫
では、小児鍼は疳の虫に効果はあるのでしょうか。
結論から言えば、効果は期待ですます。
体の硬さが取れていけば、熱が発散されていきます。
熱の具合によりますが、早いと2〜4回くらいで、疳の虫が治ることもあります。
ただ、その場合でも2〜3週間すると、徐々に熱がこもってきますから、定期的に小児鍼を受けておくと安心です。
目安は最初は週2回くらいを2週間、その後は1週間から10日くらいを目安に受けてみてください。
疳の虫の小児鍼は親御さんのため
小児鍼は子供のための鍼ですが、実は親御さんのための鍼でもあります。
お子さんの疳の虫がおさまれば、心に余裕ができますよね。
なので、子育てに困っているなら、まずは気軽に相談していただきたいと思います。
小児鍼は3分から長くても10分程度で終わります。
気軽にお立ち寄りください。
疳の虫、対処法

疳の虫は、子供(陽気の塊)に陽気がこもってしまった時に起こります。
なので、まずは熱がこもっているかを確認する必要があります。
大人も同じですが、熱がこもると、子供ながらに吹き出物ができたり、口内炎、湿疹・かゆみ、目やになどの症状がみられます。
すでに疳の虫で癇癪を起こしているなら、熱がこもっていると考えます。
でも、念の為、熱(発熱ではない)の有無や病症の度合い(深さ)を確認しましょう。
人差し指で確認
子供の検査は東洋医学では人差し指で確認します。
男の子は左手、女の子は右手の人差し指の付け根をみましょう。
その時に血管のような筋があれば、熱がこもっています。
実は色によって病症が違いますが、今回は筋があるかないかを確認してください。
指先に伸びていればいるほど病態は深いです。
自宅でのケアも大切ですが、最初の関節を越える前に小児鍼でケアすることをおすすめします。
頭をワシワシする
熱がこもっている子供の頭は冒頭でもお話ししたように硬いです。
なので、優しく頭皮をマッサージしてあげましょう。
小児鍼が効果があるのは、毛にアプローチすることで、神経(自律神経など)を刺激して体の自然治癒力に働きかけるからです。
加減が難しいですが、髪の毛を触ることをメインに頭皮をマッサージしていきましょう。
肌に優しい素材の肌着を

子供の脳は皮膚にあるに書かれているように、子供の皮膚に硬いものがあたると皮膚も固くなっていきます。
できるだけ素材の柔らかいものを身につけましょう。
また熱がこもらないよう通気性の良いものにします。
よくあるのが、冬の肌着で長袖のモコモコした肌着を着させている親御さんがいらっしゃいますが、冬も夏と同じ肌着でも構いません。
我が家は肌着に関しては、年中娘はキャミソール、息子はタンクトップです。
寒そうであれば、アウターや上着で調節してあげてください。
子供は陽気の塊なので、温めてあげる必要はあまりありません。
虚弱体質で寒がりであれば、多少加減は必要ですが、基本は厚着させなくて大丈夫です。
甘いものを控えよう

大人も同じですが、糖質を取ると血糖値スパイクといって急激に血糖値が下がります。
この下がった時に、イライラして糖質を欲していまいます。
普段からジュース(フルーツジュース含む)やコーラなどの炭酸飲料を飲む習慣があるなら、少しずつ減らしていきましょう。
果物が良いからと、夜にたくさん果物を取るのもよくありません。
できれば朝食だけにするなど、少しずつ減らしてみてください。
糖質は薬物と同じくらい中毒性(と禁断症状≒疳の虫)があるので、注意が必要です。
脂っこいものの取りすぎ注意

油は東洋医学では熱なので、取りすぎに注意しましょう。
チョコレートやスナック狩り、乳製品も熱をこもらせる原因になります。
離乳食を終えて大人と同じような食事になることからは、特に気をつけてあげてください。
唐揚げとか大好き(僕も)でしょうけど、頻繁にならないようにしましょう。
睡眠のリズムを整えよう

子供は眠たいとイライラしがちですよね(大人も同じか)。
入眠の直前は何言ってるかわからないくらい怒ってたりします(息子の事)。
なので、できるだけ夜更かしせずに入眠と起床時間は同じにして、必要であれば昼寝もしましょう。
これも大人も同じですが、睡眠不足が1日でも起こると、ホルモンバランスが崩れて食欲が増します。
常にお腹が空いた状態になってイライラの原因にもなるので、睡眠のリズムも非常に重要です。
肌が触れ合う時間を

小児鍼に勝るとも劣らないのが、お母さんやお父さんとの触れ合いです。
別にベタベタくっつく必要はなくて、ちょっと頭をなでてあげたり(さっきのワシワシ)、ボディクリームを塗ってあげたり、爪を切る時に足に座らせて切ってあげたり、工夫すると触れ合う機会は作れます。
ぜひ、お子さんに触れる時間をちょっとずつ増やしてみてください。
疳の虫、生活習慣まとめ
疳の虫は、病気ではないので、成長の段階で必要なものであったりもします。
ですが、あまりにも手を焼いて、ストレスがたまうようでは、お互いにとって良い環境ではありません。
まずは生活習慣を見直してみてください。
- 甘いものを控える
- 肌触り、通気性の良いもの着る
- ふれあいの時間を取る
すぐに全部を取り入れるのは難しいと思いますので、取り掛かれそうなものから少しずつ取り組んでみてください。
それでも、なかなか改善しない時は、一度気軽にご相談ください。
まずはお子さんの人差し指をLINEで送っていただくだけでも構いません。
一人で悩まず、ご相談くださいね。

追伸
家ならまだしも、外出中や夜中に起こるとやっかいですよね。
僕も息子が疳の虫を起こしやすいので、気をつけています。
意思の疎通が取れ始めると、会話ができてくるので、4歳くらいまでが辛抱ですね。
うちの息子は、もうすぐ4歳ですが、まだまだ手を焼いています…。
事前にお問い合わせいただいたら、親御さんが鍼灸治療を受けている間、お子さんを預かることもできますので、特にお母さんに不調があるなら、遠慮なくおっしゃってくださいね。